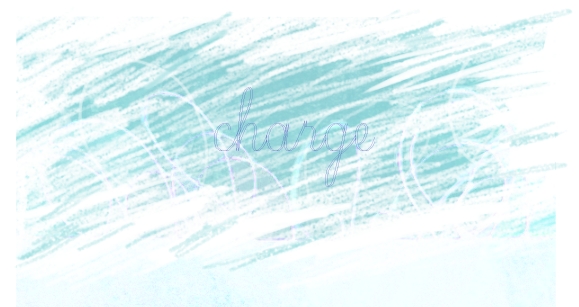 昨日降った雨のせいで、今日の気温は8月にしては低いらしい。 それでも10分歩いただけで額には汗が薄く滲むし、蝉の声は静まることを知らない。午前中は涼しいなんて事実はもう消えてなくなってしまったのではないか。そんなことを思いながら見慣れた”幸村”の文字が掘られた表札の前に立つ。 あたしが足を止めた目の前のお家は周りの景色よりも幾分か涼しげに見えた。閑静な住宅街の中の一角にあるのだから、隣の家だって負けてないくらい大きいし緑もあるのに。 この目の前の門から玄関に続く道とその横に広がる庭に丁寧に手入れされた木や色とりどりの花が植わっているこの家がどこか異国を感じさせるせいかもしれない。 そうじゃないなら、住んでいる人が暑苦しさなんてちっとも感じさせなくていつも涼しげな顔をしているからなのかも。 そんなことを考えながら、あたしは携帯をとりだして画面を触る。耳に当てるとコール音が聞こえる間もなく「着いた?」と聞き慣れた優しい声がした。 「早っ」と思わず漏れたあたしの言葉に「そろそろかなって思っていたから、携帯持って待ってたんだ」と普段は電話かメールの時以外は携帯を鞄の中にしまっている彼にしては珍しい答えが聞けた。 「鍵開いてるから入っておいでよ。俺、部屋にいるし」 さらっと言った彼の言葉にてっきり「降りるから待ってて」といつものようになると思っていたあたしは、「え、」と言葉を詰まらせた。そんなあたしを見透かした様に彼の声が携帯から続く。 「さっき母さんが買い物に行くときにが来るから鍵開けといてってお願いしてたんだよ」 「気にしないで」そんな言葉も続いて、他人の家に勝手に上がるという行為に後ろめたさを少し感じながらも何度もお邪魔しているという慣れもあって、あたしは目の前の門に手をかけた。 誰もいない玄関に「お邪魔します」と声をかけて脱いだ靴をそろえる。もしかしたら彼のかわいい妹さんが顔をのぞかせるかと思ったけれど、どうやら彼女も留守らしい。今日は平日で忙しい彼のお父さんは仕事だろうし、アクティブで多趣味なお祖母さんはこの時間はいつも俳句やお花なんかの講師をしに出かけている。 普通の家の倍くらいの幅の階段を上って彼の部屋の前に立ってノックすれば「開いてるよ」と中から声が返ってきた。 「おはよう」と声をかけながらドアを開ければ、中学生のくせにセミダブルな自分のベットにごろんと彼―――幸村精市くんが寝転んだままあたしの方に顔を向けた。 「おはよう」 「おはようって、精市くんまだそんな格好しているの?」 多分、起き上がるのが面倒くさくて、勝手に入って来て良いよ。なんて言ったんだ。あたしは思わず呆れてしまう。嬉しそうにしている精市くんはスウェット地のジャージを履いて上に薄手のパーカーを羽織ったラフな格好だ。その中には変な猫がプリントされたTシャツを着ている。 「何その猫」 「これ?かわいいだろ?」 仁王にもらったんだ。と猫を指さしながら精市くんは笑った。正直、その猫が可愛いとはちっとも思えなかった。 いつも王子様とか神の子なんて呼ばれている彼が、こんな変な服を着てごろごろしてるなんて知ったら、学校のみんなはどう思うのだろうか。 きっと仁王くんだってふざけてくれただけで、まさか本当に着ているとは思ってもないだろう。あたしはまだ起きようともしない精市くんを見て、ため息をついた。 今日はお互いに久しぶりのオフだ。夏休みとはいえお互いの部活の練習やら大会やらで、なかなか都合のつく時間の取れなかった。テニス部の全国大会も終ってあたしの部活の練習もなかった今日は、二人でどこかに遊びに行こうと約束をしていた。 なのに目の前の精市くんは出掛ける準備など何一つできていない様で、ベットの上に寝転がっている。外に出るというのに駅で待ち合わせではなく、精市くんの家に来てと言われた時から、ちょっとこういう事態は予測できてたけどね…。 「でも、母さんがにおいしいケーキ焼いたから食べてほしいっていうのは本当だよ。もうすぐ帰ってくるはずだから待っててあげてね」 あたしのジトっとした視線を返すように精市くんは笑った。 ふーん。まぁ、おばさんのお菓子って超おいしいからいいけどね。今日は何のケーキかなと考えを巡らせながら、あたしはもう一度精市くんを見た。いつもの王子様なんて言われている顔でこっちに微笑んでいるものの、その体は未だ微動だにしない。 「…精市くん」 「何?」 「いつまでダラダラしているつもりなの?」 「ええー」 可愛い子ぶった言い方に「早く着替えなよ!」と厳しく言ったら「怖い〜」と全然怖くなさそうに精市くんは笑った。 そしてベットに片手をついてようやく上半身を少しだけ起こす。ようやくって言っていいのかどうかもわからない。だって幸村くんはそのままあたしにむかって「着替えるから、服出してよ」とクローゼットの方を指したのだ。…ぐうたら…! もおー。と呆れながらもあたしはクローゼットを開く。その中はきちんと整頓されていて、どこに何があるか一目瞭然だ。 「何着るの?」 「いつものシャツ。チェックの」 「あれお気に入りだね」上から二段目のシャツの入っている引き出しを探りながら言えば「初めて着た時にがその服好きだって褒めてくれたからね」と精市くんのうれしそうな声がした。 お、覚えてない…焦りを悟られないように聞こえなかったふりをしたら「どうせは忘れてるんだろうけどね」とちょっとトゲのある言い方をされてしまった。 「下はー?何履くの?」 「うーん、カーキーのやつにしようかな」 「カーキー?珍しいね」 「たまにはね。バーバリーのやつね」 バーバリーかよ…と思いながらチェックのシャツを手にしたあたしは一番下の引き出しを開ける。カーキー色はすぐに見つかって引き出しの中にある他のものを皺にしないようにそれを引っ張り出した。 それとが適当に選んでと任せられた靴下とアンダーシャツ、どれもよく目にするブランドロゴがワンポイントでついているやつ…を手にとって、精市くんのいるベットの方へ近づいて彼の枕元に重ねた服を置いた。 「ほら、取ってきたから早く着替えて」 あたしが枕元に腰掛けてベットが沈んだせいで、精市くんの頭がちょっと浮いた。 「面倒くさいな…が着替えさせてよ」 それでも精市くんはまだやる気が出ないようで、だだっ子の様に自分の両手を万歳した。 その姿はやっぱり普段の学校生活からは考えられない。 仕方がないので精市くんの両腕からパーカーの袖を脱がして、猫のTシャツも捲り上げて袖と首からなんとか引き離す。精市くんは相変わらず寝転がったままでやりにくいったらない。反対の手順でアンダーシャツを着せてあげると、精市くんは楽しそうに笑っていた。その顔をあたしはのぞき込む。 「下は自分で履き替えてよ」 「えーどうしようかな」 どうしようかなって何だ…。 そんなことを思っていたら、精市くんはまたしても横たわったまま上にずり上がってきた。そして万歳していた腕をあたしの背にまわして、腰を挟むようにした。折っていたあたしの膝に頭をのせた精市くんは満足そうに微笑んだ。 「精市くんがこんななるの久しぶりだね」 「ん?そうかもね」 そして、あたしに髪を撫でられて目を閉じた。 彼が入院する前までは、精市くんがこんな感じで子供のようになるのは結構よくあった。普段は誰よりも自分に厳しくて、全国連覇記録を保持する立海のテニス部で頂点に立つ厳しさやプレッシャーがそれはもう、あたしには想像できないくらいにあるせいだと思う。でも退院してからはあたしと二人きりになっても、普段の神の子モードキープでこんなになることはなかった。本人に聞いても「入院中にしっかり休んだからね」と笑顔を浮かべるだけだったし。 目を開けた精市くんは深く息をついてから、あたしの目をじっと見つめ返して口を開く。 「全国大会の決勝戦、負けちゃったんだ」 一瞬だけ、黒い瞳がゆらりと淀んだ気がして、あ、泣く…と思ったけれど、それが嘘の様に次の瞬間にはいつものしっかりとした瞳に戻っていた。 「うん、知ってる」 あたしは少し癖のかかった瞳と同じ色の髪を指でそっとかき分けながら呟いた。 昨日の友達との電話で「テニス部って全国大会優勝できなかったんでしょー?」とその事実を教えられた。むこうは精市くんの彼女であるあたしが当然の様にそのニュースを知っていると思って口にしたんだろうけど、しばらく精市くんとは会ってないし連絡もとってなかったあたしは初耳で「そうみたいだね」と取り繕った。 あたしの答えに「何だ」と拍子抜けした様に呟いた精市くん。 「がどんな顔するか見たかったのに」と残念そうに呟いた。 「ごめんね、でもどんな顔して良いかわかんない」 あたしが謝ると精市くんがゆるく首を横に振ったので、少し癖のある髪が膝の上で擦れた。 「負けたのはすっごく悔しいんだけど、楽しくなったんだ。テニスが」 「楽しくなかったの?好きだったのに?」 「解らないな。好きなのは確かだけど、勝たないとっていうのが常にあったしね」 「今でもまだ抜けきってないけど…」と精市くんは呟いた。 見に行った回数は多くないけど、コートの上にいる精市くんを思い出してみる。確固たる信念、神経が研ぎ澄まされた指先、誰にも触れさせないような背中、凜としたその瞳…あれに楽しい表情がのるって? 「でも好きと楽しいって中々直結しないんだよね」 私があんまり想像できなかったように、本人にも簡単にイメージできないみたいで少し難しい顔になる。 「ふーん。あたしは部活楽しいけどな」 よくわかんないと包み隠さずに言えば、「は素直だしね」と精市くんは微笑んだ。 この人はいつも柔らかく笑うのだけれど、その芯にはとても大きなものが据えてあってテニスや自分のチームのことになると、とたんに別の人の様な顔になる。今まで自分が築きあげてきたチームの実力と結果が成せる技だ。それが良いのか悪いのか正直あたしには判断できない。でも久しぶりに会った精市くんはなんだか前よりすっきりした顔をしているし、こうやって気の抜けた姿も見せてくれている。 自分の膝の上の精市くんの顔を両手で挟み込んで、あたしはもう一度精市くんの瞳を覗き込んだ。 「でも、あたしのことは好きだし一緒にいて楽しいよね?」 「あ、それと一緒にしちゃうの?」精市くんはわざと驚いた様な顔をしてから「そうだね、たまにイラッとすることもあるけど」と優しい顔になった。 「でも精市くんが病気になった時、あたし苦しくて死にそうだった…死にそうなのは精市くんだったけど」 「あはは、そうだね。あの時は心配かけてごめんね。でもが毎日来てくれたしね」 「うん、それも精市くんのこと好きだから会いに行ってたんだよ」 「解ってる」 素直にうなずく精市くん。でも入院中の特に手術を決意する前は、彼もとてもナーバスになっていて「もう来なくていい」って何度も言われた。義務で来ているんじゃないかって、思ってたんだと思う。精市くんにかける上手い言葉を見つけられるわけでもなく、病室で沈黙が続くだけだったんだから、あたしだって逆の立場だったら絶対そう言うと思う。 家族でもないのに、学校も部活もあるのに毎日こなくたっていいって。けれど馬鹿なあたしはとにかくただ毎日精市くんの顔を見に行きたいから訪ねていたようなものだ。 もちろん病気のことは心配だったけれど、付き合ってるから毎日行かないとって思っていたわけじゃない。 それを何度も精市くんに言っては喧嘩して、やっぱりもう来なくていいなんて怒られて、同じようなことをしてた真田くんとの帰り道に慰め合って明日も絶対来ようねって言い合ってたこともあまり時は経ってないはずなのに懐かしい。 「」 あたしと同じことを思い出していたのか、精市くんが目を細めてあたしの名前を呼んだ。 「ん?」と返事をすれば「ちょっと、耳貸して」と囁いた。あたしは背中を丸めて彼の口元に耳を近づける。精市くんの腕があたしの腰から解かれて、耳に添えられる。 「もうちょっとこのままにさせて。もう少し休んだら、元気になって今日一日完璧にをエスコートしてみせるから」 耳元で精市くんの優しい声が揺れた。 あたしは一気に早くなった心臓の鼓動を彼に悟られないように、少し体を彼の顔から離す。でも真っ赤になった顔は隠すことはできなくて、精市くんに笑われた。あたしがちょっとふて腐れた顔を作れば、「ごめんごめん」と謝ってくれた精市くん。 仕方がないので、彼がズボンを履き替えるのはもう少し待ってあげよう。 -----------------------------2013.03.27 |